ご利用上の注意
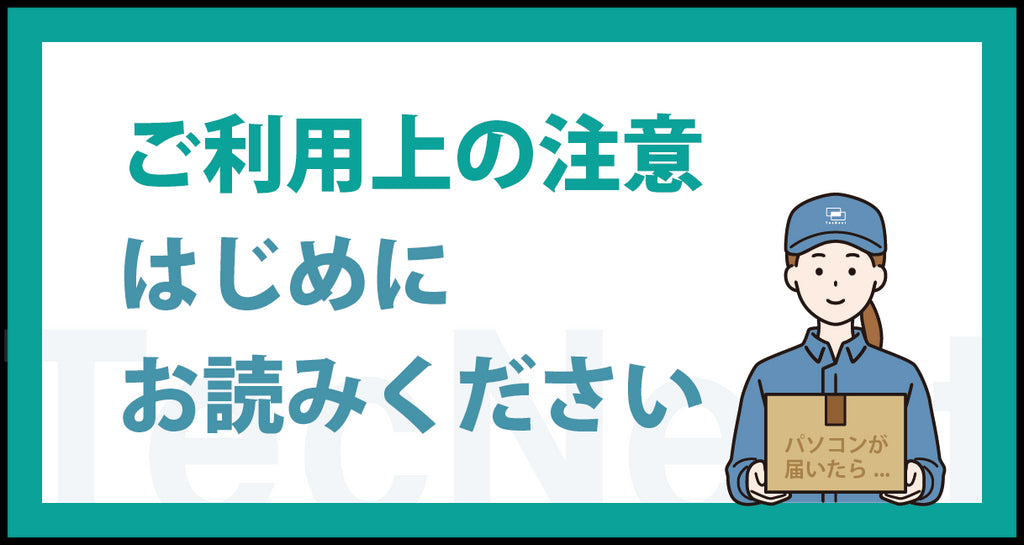
当店の商品をお買い上げいただいた方へ、パソコンのご使用方法や各種注意点などをご案内しております。
- 安全のために
- 健康のために
- 「困った💦」を未然に防いでパソコンを快適に使用するために
- 各部の名称と接続方法
1. 安全のために
安全にご利用いただくために
パソコンは、安全にご利用いただけるよう、各規格に準拠したパーツにて製造されております。また、当店で販売している中古パソコンも安全基準を満たせるようメンテナンスを行っております。しかし、接続や使用方法が正しくないと、火災や感電などの事故を引き起こすことがあり危険です。事故を防ぐために、記載事項を必ずお守りください。
定期的に点検する
パソコンは精密機器なので、ケース内にホコリがたまると誤作動の原因となります。ケースファンにホコリが付着すると冷却性能低下によるトラブルが発生しますので、定期的に点検・清掃をしてください。
故障した場合
パソコンを使用していて何らかの問題に気付いたとき、または問題が解決できない場合は、下のリンクよりお問い合わせください。
異常が起きたら
異音・異臭・煙が出たら、即時ご使用をお止めください。
直ちに使用を中止し、電源を切り電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
当店へ【お電話(03-4334-8845)】か下のリンクから点検・修理をご依頼ください。
使用環境
パソコンの設置場所および使用環境については、以下の条件でご使用ください。この条件以外でパソコンを使用すると、火災などの事故や、パソコンが破損する、起動しなくなるなどのトラブルの原因となります。
次のような場所が設置に適しています。
- 室内
- 温度 10℃~35℃
- 湿度 20%~80%(結露しないこと)
極端に温度が低い室内で電源を入れるとパソコンが起動しないことがあります。そのような場合は一度電源を切り、室内の温度を上げて2時間ほど放置してから電源を入れ直してください。急激な温度の変化で内部に結露が生じ、部品がショートして故障の原因となるのを防ぎます。
設置場所の警告・注意
 警告
警告
 |
水槽の近くや水場のそばなど湿気の多い場所には設置しないでください水がかかりますと、火災や感電の原因となります。 |
 |
幼児の手の届く場所に置かないでくださいディスクの挿入口に手を挟まれたり、ケース内の鋭利な個所等が、けがの原因となります。 |
 |
テーブルタップ等を使用する場合は、接続する機器の容量がテーブルタップの容量を超えないようにしてください火災や感電の原因となります。 |
注意
 |
家電製品のそばや磁気を発生させる物の近くには設置しないでください異常動作の原因となりますので30cm以上離して設置してください。 |
 |
直射日光のあたる場所やストーブの近くなど、熱くなりそうな場所には設置しないでください変色、変形等の劣化の原因となります。 |
 |
パソコンの通風口をふさがないでくださいパソコンパーツの多くは発熱します。パソコンの排気口や通風口をふさぐと、本体内の空気の換気がうまくいかず、本体内部温度が上昇してパソコンの誤作動や故障の原因となります。必ず10cm以上離して設置してください。 |
 |
屋外やホコリの多いところには設置しないでください火災や感電の原因となります。 |
 |
不安定な場所に置かないでくださいぐらついた台の上や傾いた場所に置くと、製品が落ちてけがの原因となります。また、置き場所、取り付け場所の強度にも十分に確認してください。 |
 |
コンセントから電源プラグを抜きやすいように設置してください万一の異常や故障、または長期間使用しないときなどに役立ちます。 |
 |
スリム型パソコンを縦置きでのご使用の場合は台座をご使用ください底面の吸気口がある場合、吸気口をふさぐと、本体内の換気が正常に行われず、本体内部温度が上昇してパソコンの誤作動や故障の原因となります。 スリム型デスクトップパソコンは揺れや振動により不安定になる場合があります。 |
本体使用上の警告・注意
警告
 |
「異音がする」「焼けたような匂いがする」「ケーブルやコネクタが異常発熱している」などの場合直ちに使用を中止し電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。そのまま使用されると、火災や感電の原因となります。 その後の処置は、当店カスタマーサポートまでご相談ください。 |
 |
内部に水や異物を入れないでください水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一入り込んだ場合は、すぐに電源を切り電源プラグをコンセントから抜いてください。 その後の処置は、当店カスタマーサポートまでご相談ください。 |
 |
パソコンが変形していたり、亀裂などの破損個所がある場合は使用しないでください破損があるパソコンを使用すると、火災・感電の原因となります。その場合は直ちに使用を中止し、電源を切り電源ケーブルをコンセントから抜いてください。 その後の処置は、当店カスタマーサポートまでご相談ください。 また、当店では「訳あり」品として破損個所のあるジャンクPCも販売しております。ご使用の際は自己責任でご利用ください。 |
 |
改造しないでくださいパーツの分解・改造をしないでください。 |
 |
アダプターや周辺機器などを接続する際はコネクタの向きを確認し、変形や破損がないかも合わせてご確認ください・コネクタの向きを間違って接続すると、変形や破損の原因となります。 |
 |
雷が鳴り始めたら、パソコンを終了してコンセントやLANケーブルを抜いてください落雷により感電したり、故障の原因となります。 |
 |
電源や周辺機器などを接続したケーブルやコネクタに無理な力を加えないでください「机の脚で踏む」「無理な角度でコンセントを差す」などケーブルやコネクターに無理な力が加わると、変形や破損による火災・感電の原因となります。 |
 |
電源ケーブルを傷つけないでください電源ケーブルを傷つけると、火災・感電の原因となります。 ■重い物を乗せたり、引っ張ったりしない |
 |
濡れた手で電源プラグに触らないでください感電の原因となります。 |
 |
ケーブルのコネクタを抜くときはケーブルを持たず必ずコネクタ部分を持つようにしてくださいケーブルを直接引っ張ってコネクタを抜くと、ケーブル断線などの故障の原因になります。取り外すときは必ずコネクタ部分を持つようにしてください。 |
 |
電源プラグや各種コネクタ、周辺機器などを接続したまま移動させないでくださいケーブルやコネクタ等が破損・変形することによる、火災や感電の原因となります。 |
注意
 |
長期間使用しない場合はコンセントを抜いてください火災の原因となります。 |
 |
電源プラグを挿したまま、メンテナンスなどのケース内の作業を行わないでください作業時に感電・けが・破損の原因となります。 |
 |
電源切り替えスイッチがある場合は必ずAV115V側で使用してください |
 |
長時間使用する場合は、必ず途中で休憩をとるようにしてください肩こり、腰痛、目の疲れ、腱鞘炎などの原因となります。 |
 |
長時間の使用などにより、身体に違和感や痛みを感じた場合は直ちに使用を中止してください使用を中止しても改善しない場合は直ちに医師に相談することをお勧めします。 |
2. 健康のために

| 姿 勢 |
▶腰を背もたれに密着させましょう。 ▶腕や太ももは床と平行にしましょう。 ▶足裏全体を床につけるようにしましょう。 |
| キーボード マウスの操作 |
▶マウスを動かす際は、手首だけを使わずに腕全体で動かすようにしましょう。 ▶キーボード入力中は、手首と手を宙に浮かせ、離れたキーを押すときに指を伸ばすのではなく腕全体を移動させるようにしましょう。 ▶キーボードやマウスは軽いタッチ・クリックをしましょう。 |
| 使用時間 |
|
| ディスプレイ |
▶ディスプレイの上の部分が目の位置より少し下にくるようにしましょう。 ▶ご利用中、外光が目に直接入ったり、画面に映りこまないようにしましょう。 ▶ディスプレイは清潔にしましょう。 |
3. 「困った💦」を未然に防いでパソコンを快適に使用するために
 |
パソコンやパソコンの周辺を清潔に保つ空気中のチリやホコリは精密機器であるパソコンの大敵です。パソコンや、パソコンの周辺を常に清潔に保てるよう心がけましょう。
|
 |
正しい方法で電源を切るやむを得ない場合を除き、電源スイッチを押して強制的にパソコンの電源を切ることはおやめください。パソコンが故障したり、正常に動作しないなどのトラブルを引き起こす原因となります。 |
 |
パソコン使用時の飲食、喫煙は避ける飲食をしながらパソコンを使用すると、食べ物や飲み物がかかり、パソコンを故障させる原因となります。また、タバコの煙や灰は精密機器であるパソコンにとっての大敵ですのでご注意ください。 |
 |
作業中はこまめにデータを保存する「パソコンが突然フリーズ(停止)して作成中のデータが消えてしまった」ということがないよう、文章作成などの作業時はこまめにデータを保存しましょう。 |
 |
定期的にデータのバックアップを作成する誤った操作やウイルス感染などにより、ハードディスク内のデータが消えてしまうことがあります。 |
 |
パソコンにショックを与えない電源が入っている/いないに関わらず、パソコンにものをぶつけたり倒してしまうなどのショックを与えないよう十分ご注意ください。肘をぶつけるなど、ほんの少しのショックでもハードディスクや内部パーツが破損したり、フリーズ(停止)状態になってしまうことも稀にあります。 |
 |
インターネットを利用するときはウイルス対策を万全にインターネットに接続すると、Eメールやウェブサイトなどからコンピューターウイルスに感染する危険があります。そのため
|
4. 各部の名称と接続方法(デスクトップ背面)
一般的なデスクトップパソコンにおける各コネクタと端子の接続方法を説明します。下記の順番で接続してください。
- ディスプレイケーブルを接続する
- キーボード・マウス(機器)を接続する
- ネットワーク機器(モデム・ルーター)を接続する
- オーディオ機器(スピーカー、マイク等)を接続する
- 電源ケーブルを接続する

ディスプレイを接続する(I/Oパネル・拡張スロットエリア)
画面を表示するためにディスプレイを接続します。
※ビデオカードが搭載されている場合といない場合では、接続する場所が異なりますのでご注意ください。
ビデオカード(グラボ)が搭載されている場合
搭載されたビデオカードにディスプレイ端子があります。
下図を参考にディスプレイケーブルを接続してください。また、ケーブルや端子の種類については下記【ディスプレイとパソコンの接続方式】をご覧ください。

※注:マザーボード側にあるディスプレイ端子に接続した場合、画像が表示されない場合があります。必ずビデオカードの端子に接続してください。
ビデオカード(グラボ)が搭載されていない場合
マザーボード側にあるディスプレイ端子にディスプレイケーブルを接続してください。

ディスプレイとパソコンのケーブル配線について
パソコンとディスプレイは一本のディスプレイケーブルで接続します。パソコンとディスプレイを接続する方法は複数ありますが、一台のディスプレイにつき同時には使用できません。パソコンとディスプレイ両方に適合する接続方式のディスプレイケーブルで接続してください。
複数のケーブルでパソコンとディスプレイを接続された場合、ディスプレイが正常に表示されませんのでご注意ください。

※注:ケーブルには接続方向が定まっているものもあります。ケーブルに刻印された表記、またはご購入されたケーブルの説明書をご参照ください。
ディスプレイとパソコンの接続方式
ディスプレイとパソコンの接続方式はアナログ接続の【D-Sub15ピン】やデジタル接続の【DVI】【HDMI】などがあります。接続する際はデジタル接続を優先して使用しましょう。
デジタル接続の方が最大解像度が大きく鮮明な画像で表示されます。
また、HDMI / DisplayPort接続の場合は同時に音声信号も出力され、HDMI / DisplayPortの音声入力に対応したスピーカー搭載ディスプレイを接続すれば、ディスプレイから音声が出力されます。
※使用できる接続方式は、本体またはディスプレイの構成によって異なります。

ワンポイント
複数のディスプレイを使用する際に、接続できる端子が足りない場合があります。接続端子が足りない場合には、変換コネクターや変換ケーブルを使用して接続することができます。
※変換コネクタは様々な種類があり、コネクタのオス・メスなどの違いもあります。必要な組み合わせをよく確認してご準備ください。
※パソコンによって接続できるディスプレイの数は決まっています。接続端子が複数台分あっても同時に使用できる台数に制限があるものがありますので、接続できる最大台数をあらかじめ確認しましょう。
※ディスプレイケーブル・変換コネクタの中には、パソコン方向やディスプレイ方向などの接続方向が定まっているものがあります。パソコンと接続しても画面が表示されない場合、接続方向を確認しましょう。
※ディスプレイにも電源接続が必要となります。パソコンと接続しても画面が表示されない場合、ディスプレイの電源接続を確認しましょう。
キーボード・マウス(USB機器)を接続する(I/Oパネルエリア)
パソコンを操作するためにキーボード・マウスなどの機器をUSB端子に接続します。
キーボード・マウスは有線ケーブルで接続するか、無線接続の機器の場合は無線子機(USBレシーバー)をパソコン側のUSB端子に接続しましょう。
※無線接続機器の中にはUSBレシーバーが必要ない機種もあります。その場合Bluetooth接続を行います。
その他にもWi-FiレシーバーやBluetoothレシーバーなど無線接続の子機などを接続する必要がある機種もあります。
USB接続する端子の注意
キーボード・マウスをUSB端子に接続する際は、USB 2.0の端子に接続を行ってください。USB 3.0の端子に接続した場合、正常に動作しないことがあります。

※USB2.0とUSB3.0の端子見分け方
端子の色を確認しましょう。通常USB3.0の端子は青色をしています。
ですが、機種によりUSB2.0、USB3.0ともに異なる色をしている場合もあるので、詳しくは説明書などを参照しましょう。
パソコン側にPS2端子がある場合、USBからPS2に変換するプラグを使用すると、PS2コネクタでマウスまたはキーボードを使用することができます。

ネットワークへ接続する(I/Oパネルエリア)
インターネットに接続するためにネットワーク機器を接続します。

モデム・ルーター・ハブなどからLANケーブルをパソコン側のLAN端子に接続しましょう。
※ノートパソコンなどの機器の中にはLAN端子がなく、Wi-Fiによりネットワークへ接続するものもあります。
※ネットワークへ接続できない場合
有線LANを接続してもネットワーク接続できない場合やWi-Fiも受信しない場合はネット回線の問題、もしくはパソコン内部のネットワーク部品の故障やドライバの異常などのトラブルが考えられます。当店へご相談いただくか、USB端子へ接続するWi-FiレシーバーまたはLANアダプターなどをお試しください。
スピーカーを接続する(I/Oパネルエリア)
サウンドを出力するためにスピーカーをオーディオ端子へ接続します。
デスクトップパソコンの多くは、サウンドカードを搭載しなくてもマザーボードのオンボード機能で7.1chのサウンド出力に対応しています。
また、パソコン本体前面にも端子がある場合、前面と背面のいずれか片方しか使用できません。音が出ない場合には、片方のみで接続してください。
それぞれの端子の役割は以下の通りです。
 |
サイドスピーカー用 | ※ステレオ・スピーカーと接続する場合は、緑の端子のみを使う。 ※5.1chスピーカーと接続する場合は、白い端子(サイド・スピーカ用)以外の3本と接続。 |
 |
リアスピーカー用 | |
 |
センタースピーカー/サブウーファー用 | |
 |
フロントスピーカー用 | |
 |
ライン入力 | ※音響機器からのライン出力端子を接続。 |
 |
マイク入力 | ※マイクと接続。 |
 |
S/P DIF(光デジタル音声端子) | 光ファイバーケーブルで音声信号をデジタル出力する規格。SonyとPhilips社が共同開発したデジタル・インターフェースS/P DIF。 |
電源ケーブルを接続する(電源エリア)
電源を供給するためにコンセントから電源端子へケーブルを接続します。
※電圧切り替えスイッチがある場合、115V側になっていることを確認します。230V側になっている場合はスライドさせて必ず115V側に設定しましょう。

電源端子に電源ケーブルを接続する際、向きを合わせて取り付けてください。
電源スイッチは、接続がすべて完了するまでOFF(「〇」印がある側)にしておきます。接続がすべて完了した後にON(「|」印がある側)にしてください。
製品に同梱されている電源ケーブルをご利用ください。
同梱されている電源ケーブルはほかの製品には使用しないでください。
またたこ足配線は発熱・火災の原因となったり、電源の供給不足からパソコンの動作が不安定になる場合がありますので、家庭用電源コンセントから直接電源をお取りください。
シェア:

